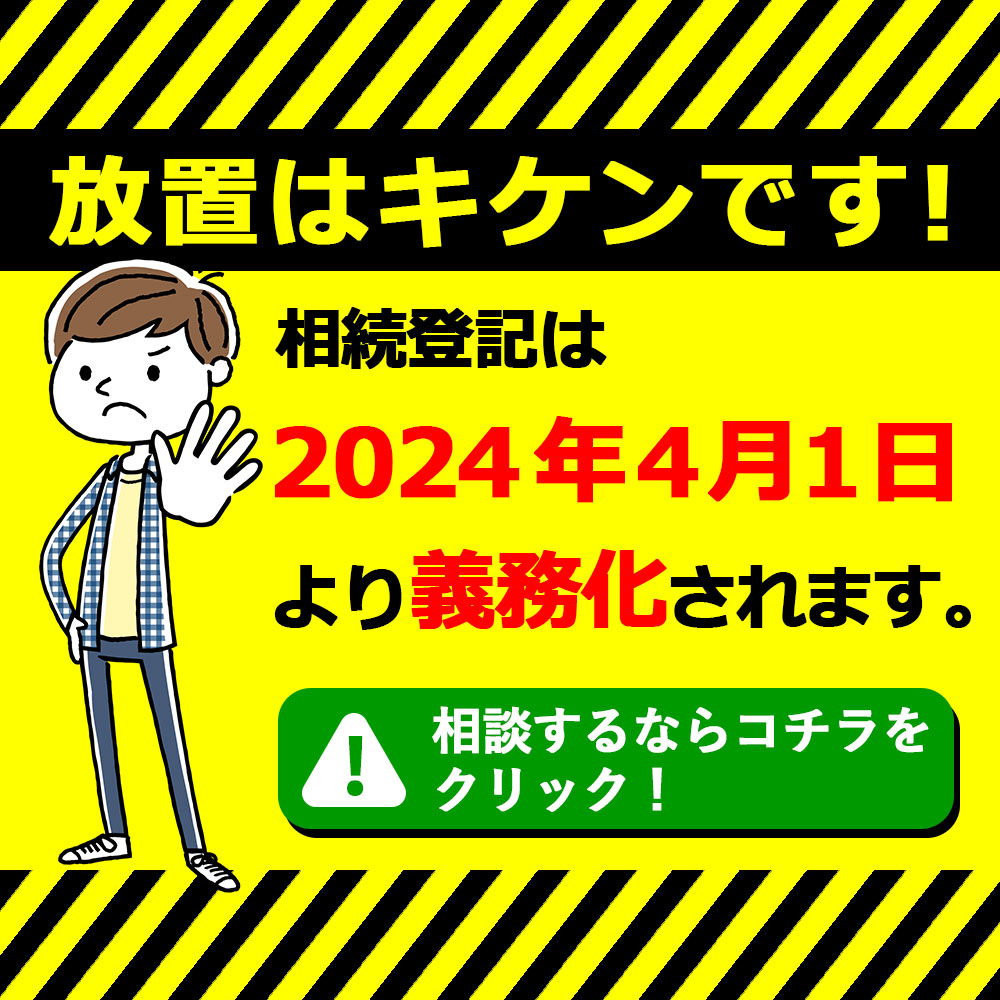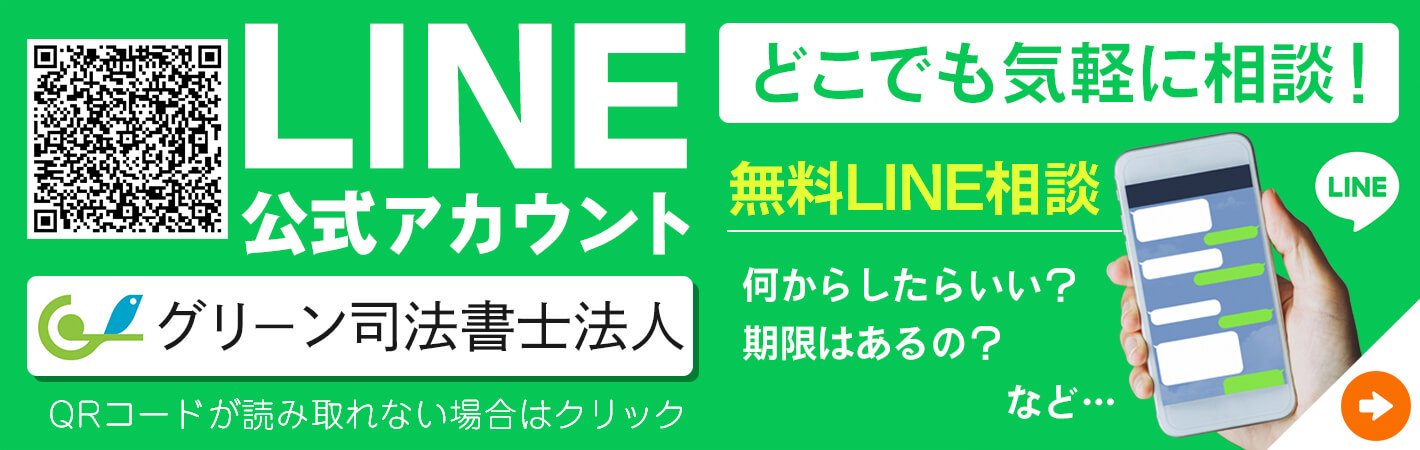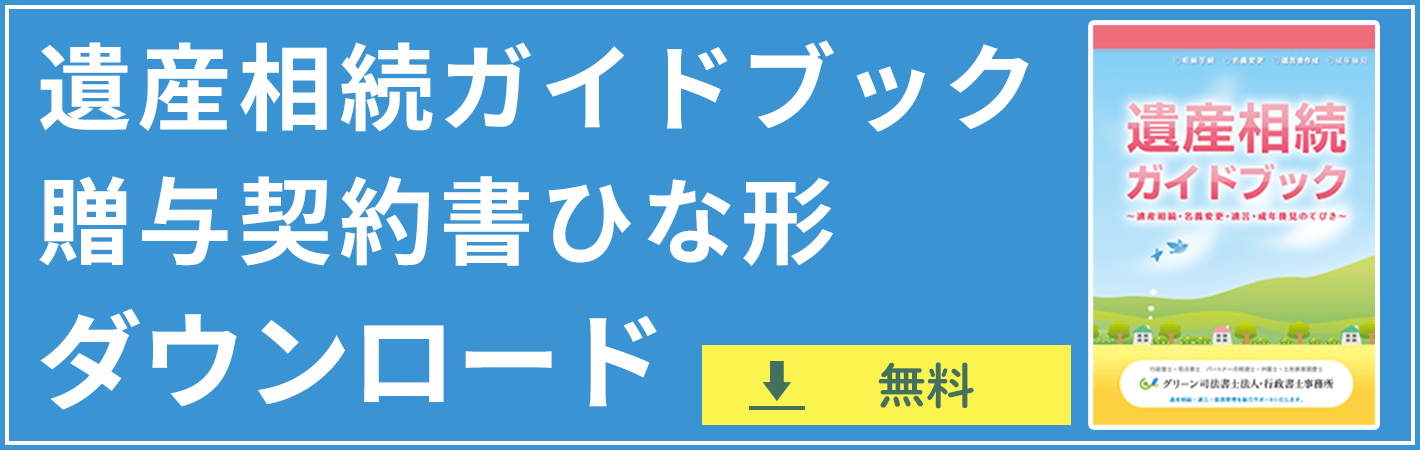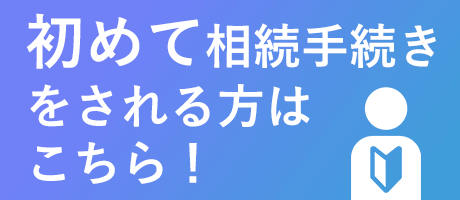被相続人が認知症だった場合に、確認しないといけないこと2点

山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続手続きにおいて、誰がどのくらいの財産を相続するのかは法律でルールが定められています。
そして被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が遺言を残している場合は、基本的にその遺言の内容が優先されます。
しかし、被相続人が生前認知症と診断されていたり、認知症の疑いがあったりする場合は、その遺言や生前に行った贈与、相続税対策として行っていたことなどは有効なのかという問題がでてきます。
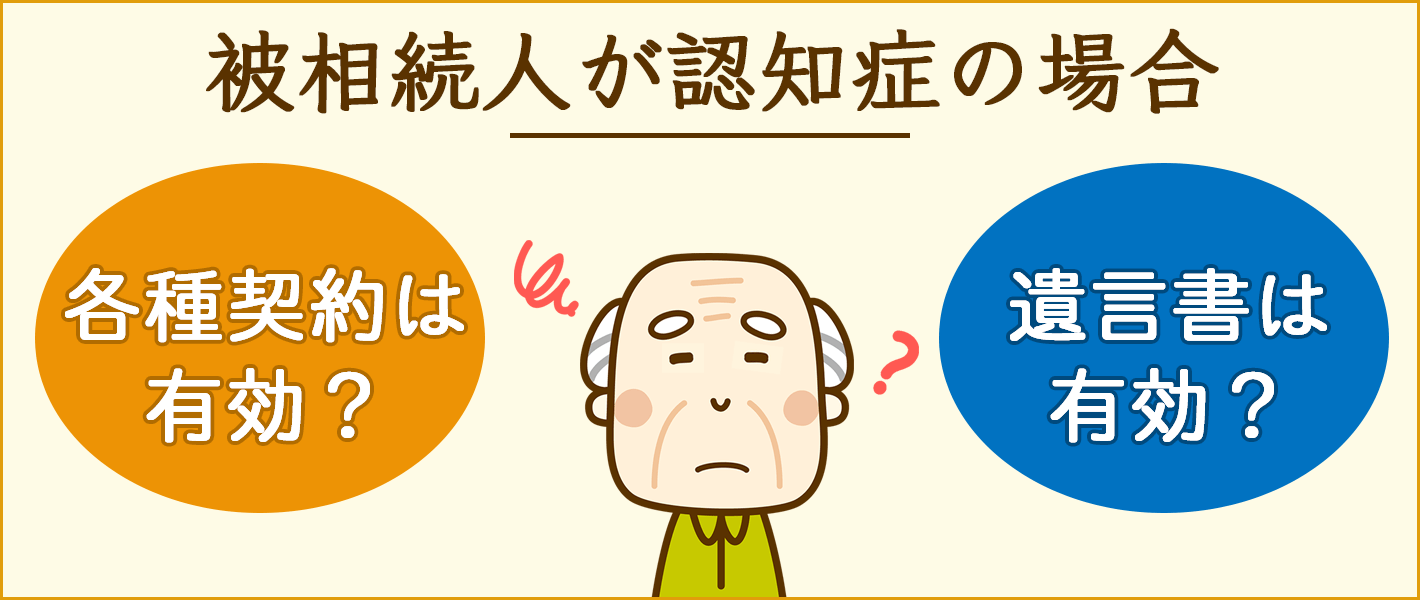
大きくわけて、「被相続人が行う各種の契約は有効かどうか」「被相続人が残した遺言書は有効かどうか」の問題が考えられます。
目次 [ 閉じる ]
認知症の被相続人が行う各種の契約は有効か?
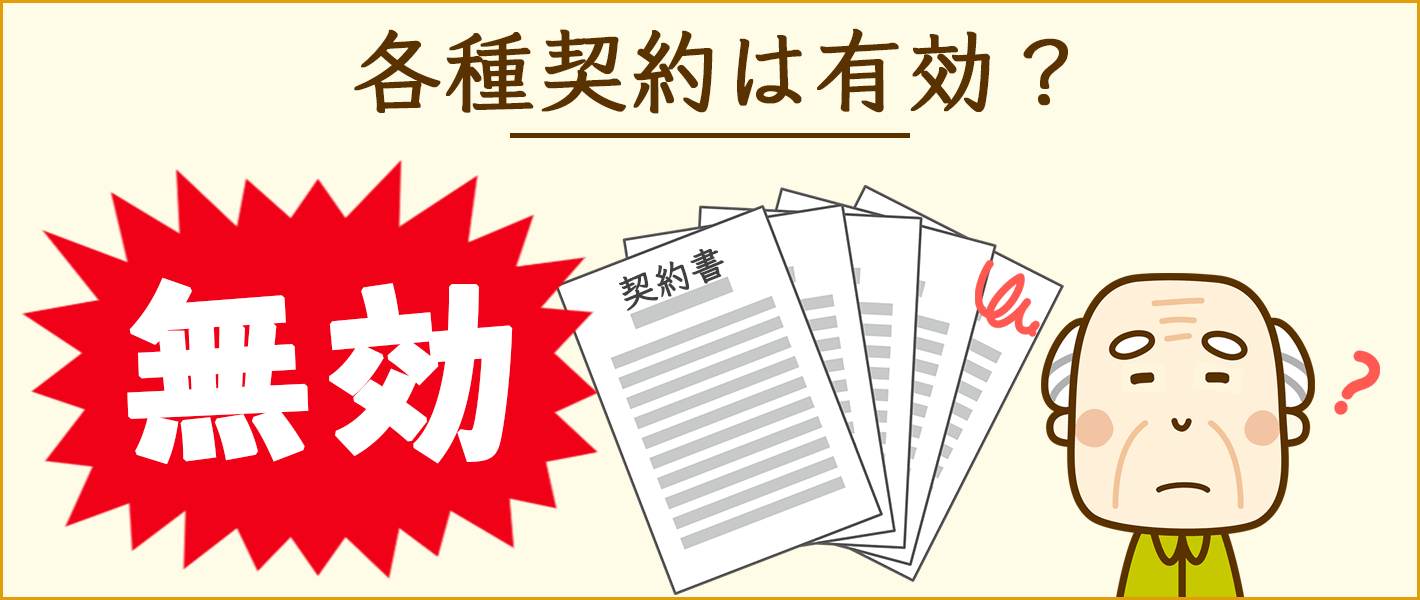
正常な判断能力を欠いている方が行った法律行為は無効とされています。
法律行為とは、売買契約や贈与などの法律的な効力がある各種行為のことをいいます。
被相続人が認知症と医師から診断されている場合は、正常な判断能力が欠けているとみなされる可能性が高く、被相続人が行った法律行為は無効と判断される可能性が高くなります。
無効とは簡単に言うと「どのような証拠が残っていたとしても、行為が行われた時点にさかのぼって全ての効力が否定される」ということです。
契約書自体に不備はなく、正式な契約書だとしても、その契約書を作成した時点で作成した本人に正常な判断能力があるかどうかが重要な基準となります。正常は判断能力がなかった場合は、契約は全くなかったことになってしまうのです。
認知症の方が契約するために支払ったお金は返還する必要があり、土地や建物を引き渡した場合は持ち主に返す必要があります。
まだら認知症の場合
しかし、「まだら認知症」の場合は有効と判断される可能性があります。
まだら認知症とは、1日のうちで正常な判断能力があるタイミングと、そうでないタイミングがある場合や、物忘れはひどいがその他は問題なく正常に判断できる場合の認知症の症状のことをいいます。
被相続人がまだら認知症の場合は、契約などの行為を行った時点で正常な判断能力があったのか、が有効性をめぐって問題となります。
正常な判断能力があったと認められると有効な契約となるので、被相続人がまだら認知症の場合は全ての法律行為が無効になるわけではありません。契約などの行為を行った時の状況が大事な判断基準となるのです。
その判断は、裁判所が残されている各種証拠資料を参考に判断することになるので、しっかりと残しておきましょう。
認知症の被相続人が残した遺言書は有効か?
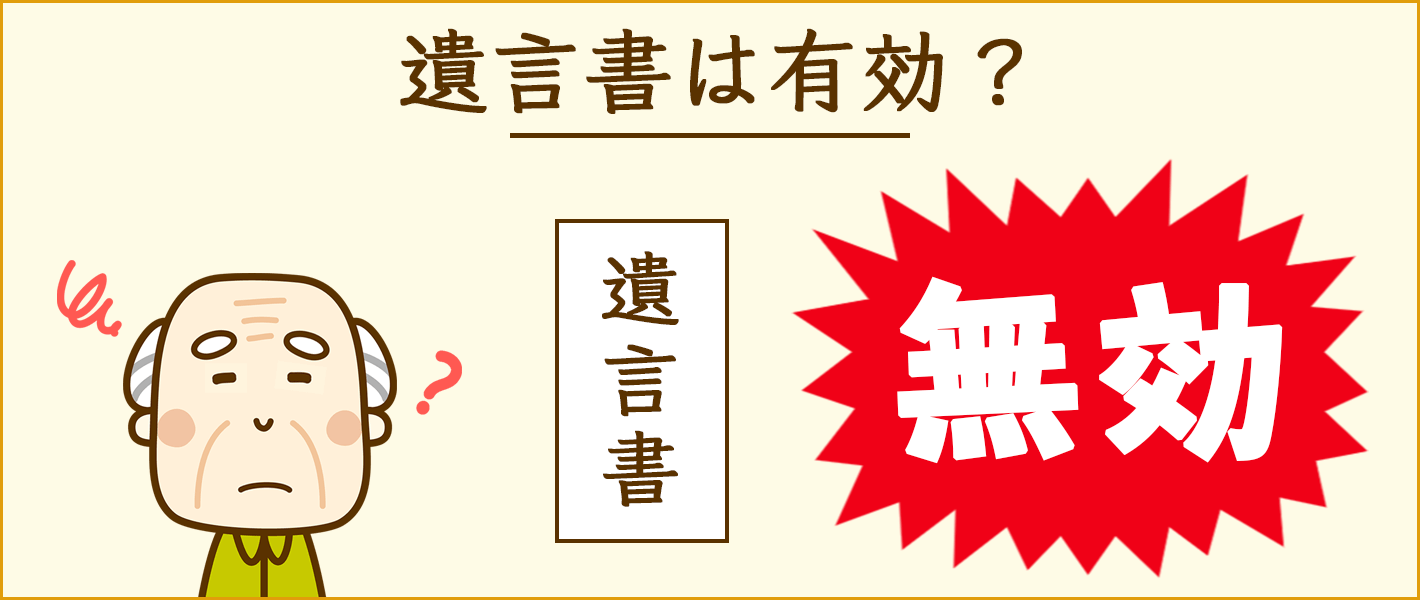
遺言を残しているが、被相続人が認知症の場合は、その遺言が有効か無効かが問題となります。
遺言については法律でルールが決められており、遺言を作成した時に認知症などにより正常は判断能力がなかった場合は、その遺言は無効とされてしまう可能性があります。
遺言の有効性は裁判官が判断
遺言の有効性が裁判で問題になったときは、遺言が作成された時点の状況をみて、遺言作成者に正常な判断能力があったのかを裁判官が判断します。
医師の診断書があれば重要な根拠となると考えてしまいますが、あくまで法律的な問題においては医師の診断書は参考資料なので、他にも具体的に証拠を残しておきましょう。
最終的に有効性の判断をするのは裁判官で、過去の裁判例を参考に遺言が有効と判断されるか予測して対策していきましょう。
公正証書遺言を作成しておきましょう
遺言は自筆で作成する「自筆証書遺言」でも正式な形式で作成されていれば問題なく効力を発揮するのですが、認知症問題の対策としては公証人役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめします。
公正証書遺言は、公証人役場で公証人の立ち合いのもとで作成する遺言なので、遺言作成者に認知症の疑いがあり、後々有効性に関する問題が発生した場合でも無効とはならない可能性が高いのです。
なお、被相続人に認知症の疑いがある場合の遺言が全て問題になるということはなく、相続人全員が遺言の内容に納得し争う人がいない場合は、その遺言は成立します。
被相続人が認知症の場合の相続対策
被相続人に認知症の疑いがある場合は、相続トラブルに発展しないように対策を行っておく方が安全です。
対策としては、後見制度を利用して認知症の方の代わりに行為を行う人を決めておくことです。
後見制度とは、家族や専門家が認知症の方に代わって法律行為を行えるようにする制度で、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類あります。
任意後見制度を利用すると
任意後見制度は将来的に認知症になってしまった時に備える場合に利用でき、すでに認知症を発症してしまっているなどで判断能力がない場合は、法定後見制度を利用することになります。
任意後見制度では、将来的に判断能力が低下してきた時の後見人となる人を事前に契約で決めておきます。(公正証書で契約書を作成して、任意後見契約をします。)
任意後見人は、家族でなくても司法書士や行政書士などの専門家に任せることもできます。相続財産が多く専門的な知識が必要な場合は専門家に任せることも検討しましょう。
認知症の症状が現れてきたら、家庭裁判所に任意後見契約を有効にしてほしいと申立を行い、家庭裁判所の審判がでると任意後見契約が有効になります。
家庭裁判所は任意後見人が本人の不利益になるような法律行為を行わないか確認する「任意後見監督人」を選任してくれるので、任意後見人と任意後見監督人で認知症となった方の利益を守ることができます。
任意後見契約を結ぶ前に、認知症と診断されている場合は任意後見制度を利用することができません。
認知症と診断されている方は、全ての法律行為ができなくなるので、任意後見契約を締結することができないからです。
すでに認知症と診断されている場合は、次に紹介する法定後見制度を利用します。
法定後見制度を利用
法定後見制度は、すでに認知症と診断された方にも、家庭裁判所に申立てを行う事で後見人となる人を選任してもらうことができる制度です。
しかし、法定後見人は本人の不利益になるような行為ができないので、法定後見制度を利用して相続対策を行う場合は問題が起こりやすくなる可能性があります。
例えば、法定後見人となった家族が将来の相続税対策で生前贈与を行いたいと考えても、それは家族の人の利益のために行う行為であり、本人の利益にはならないとみなされてしまう可能性が高いのです。
上記のように、法定後見人が家族の財産を守るために相続対策を行いたくても、その行為が本人の不利益とみなされてしまいできないのです。
認知症になってしまうと手遅れ?
相続対策は基本的に残された家族のために行う行為で、本人(認知症となった方)にとっては財産を贈与すると財産が減るのでデメリットとなるのです。
そのため多くの場合、法定後見人が行う相続対策は認められない可能性が高くなります。
認知症になってしまうと、相続対策としてできることは極端に制限されてしまうので、認知症になる前に相続対策を行っておきましょう。
下記ページで、成年後見制度について詳しく説明しているので、ご参考にしてください。
成年後見とは? 成年後見の失敗事例相続人の中に認知症の方がいる場合について
被相続人が認知症だった場合の対応などについてご説明してきましたが、相続人の中に認知症の方がいる場合もあります。
相続人の中に認知症の方がいる場合、どのような対応が必要なのか、解決事例について下記記事でご紹介しておりますので、ご参考ください。
相続人が認知症の場合について認知症関連の解決事例をご紹介
合わせて読みたい記事
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事