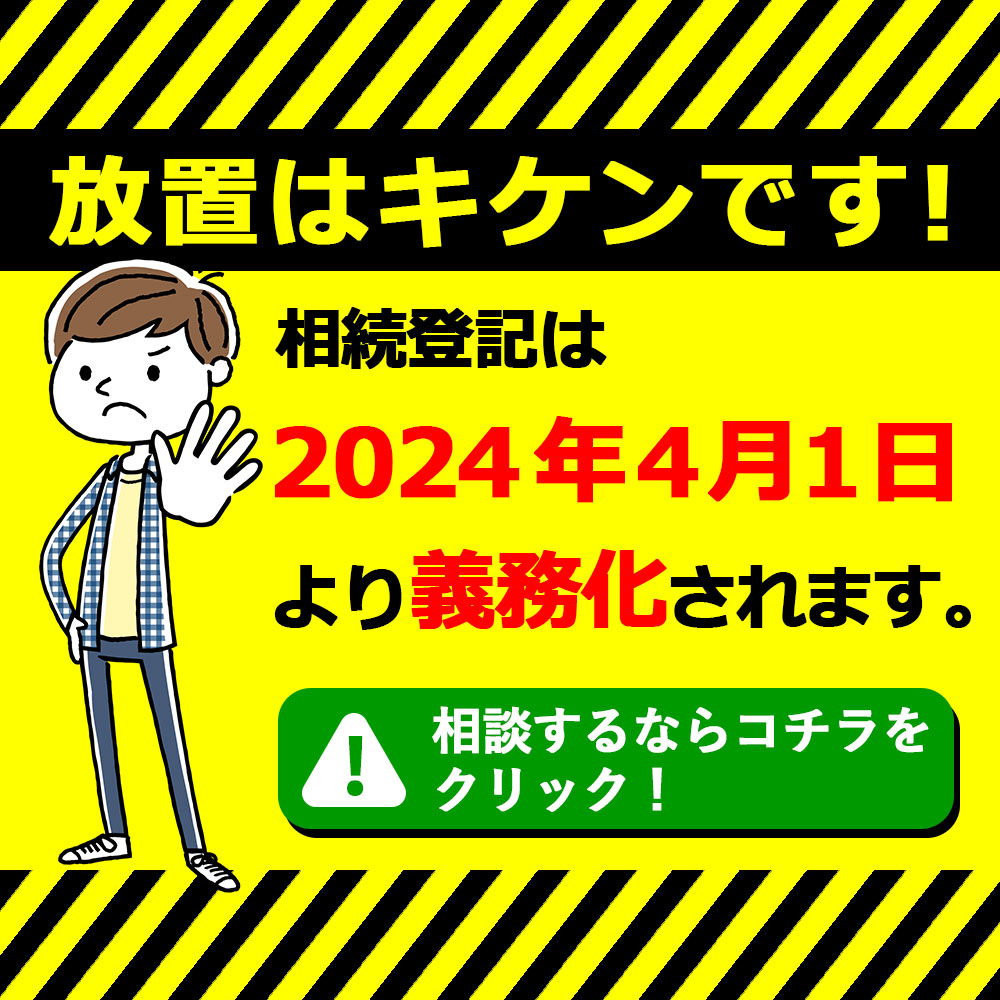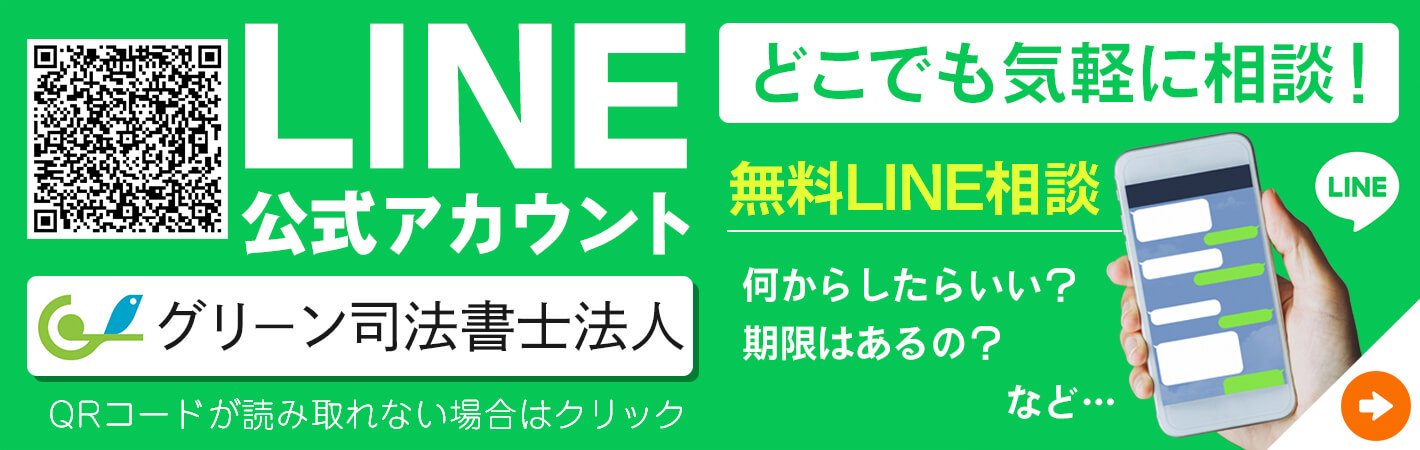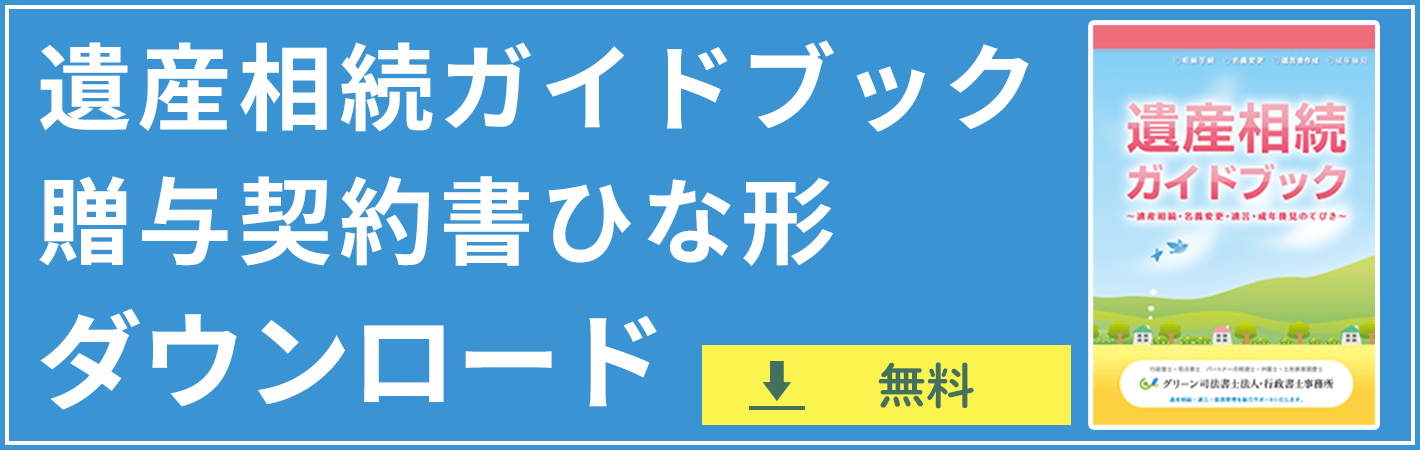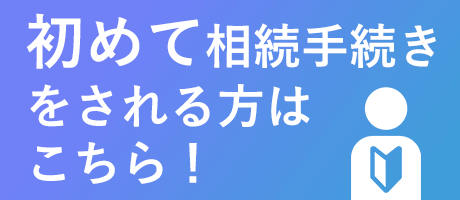夫婦間の贈与で贈与税は発生する?しない?特例を活用するには

山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
夫婦間であっても贈与をすると贈与税が発生する場合があることをご存じでしょうか。
どのような場合に贈与税が発生するのか、発生しないのかについてお話しし、特例についてもわかりやすく解説していきます。

目次 [ 閉じる ]
夫婦間でも贈与税が課税される場合
夫婦間で金銭のやり取りをしたり、金銭的負担を肩代わりしたりすることは日常的にあるかと思います。
金銭のやり取りすべてに贈与税が発生するのではなく、下記のような場合に夫婦間でも贈与税が発生します。
- 夫名義の住宅ローンの頭金を妻が負担した場合
- 住宅ローンは夫名義で組んで、登記は夫婦の共同名義の場合
- 夫名義の住宅ローンを、妻の資金で返済した場合
- 夫名義の住宅のリフォーム費用を妻の資金から支払った場合
上記のように、不動産の購入に関して贈与税が発生する場合や、口座間での多額の預金移動が贈与とみなされる場合があります。
ですが、贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、夫婦間で贈与をしたとしても基礎控除内であれば贈与税は発生しないので、ご安心ください。
たとえば、夫名義の住宅ローンの返済を、月々7万円、妻の資金から支払ったとすると、年間84万円なので、基礎控除の年間110万円の中に収まるため相続税が発生せず、贈与税の申告や納税をする必要がありません。
ほかに贈与があり合計で基礎控除額を超えてしまうと贈与税が発生しますので注意しましょう。
年間110万円の基礎控除額を超えた場合は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日(休日の場合は翌日)の間に贈与税の申告を行い、納税を行いましょう。
夫婦間贈与で贈与税が非課税になる場合
夫婦間の贈与で贈与税が非課税になるのは、生活費と教育費です。
なぜかというと、夫婦や家族間には扶養義務があり、通常必要と認められる生活費や教育費をやり取りする場合、贈与税は発生しないと決められているからです。
国税庁のホームページなどで、【生活費や教育費などの通常必要と認められるものについては課税対象にならない】と書かれています。
国税庁/贈与税がかからない場合ですが、生活費や教育費として贈与されていても、他のものに使用すると贈与税の対象となりますので注意しましょう。
生活費や教育費として夫婦間で贈与する場合は、必要な金額を必要な時に行うようにすることをおすすめいたします。
そして、あまりに金額が大きい場合や贈与の回数が多い場合は、生活費や教育費と言っても認められず贈与税が発生してしまう場合もありますので、併せてご注意ください。
夫婦間贈与の特例について
夫婦間贈与には配偶者控除という特例があり、「婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円にプラスして最高2,000万円まで、合計で最高2,110万円まで贈与税を控除できる」というものです。
また、贈与税の配偶者控除を受けた財産については、「相続開始前3年以内」であっても、税法上、相続財産への加算の必要はありません。
特例を受けるための適用要件
夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること
または国内の居住用不動産を取得するための金銭であること - 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
建物もしくはその敷地のことで、建物のみ、敷地のみ、建物と敷地、いずれの場合も可能です。
また、店舗兼住宅のような不動産の場合は、居住用部分についてのみ適用が可能です(居住用部分の面積がおおむね90%以上のときは、全部を居住用として扱うことが可能です)。
その他、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産もしくは贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、受贈者が現実に住み、その後も継続して居住する見込みであることが必要です。
適用を受けるための手続
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
- 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
- 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明証
- その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
- 金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
- 贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。
贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)
- 居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能。
※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
不動産価格の算定
- 建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
- 土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。
合わせて読みたい記事
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事