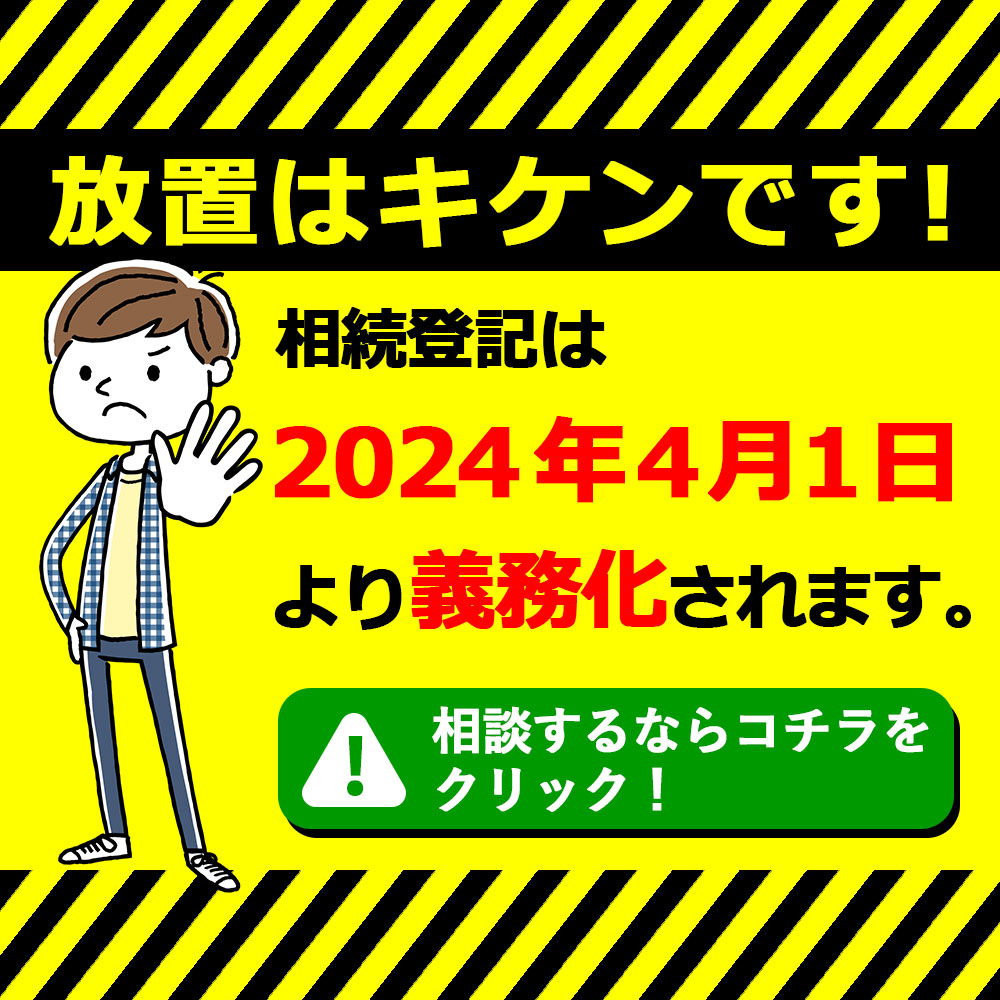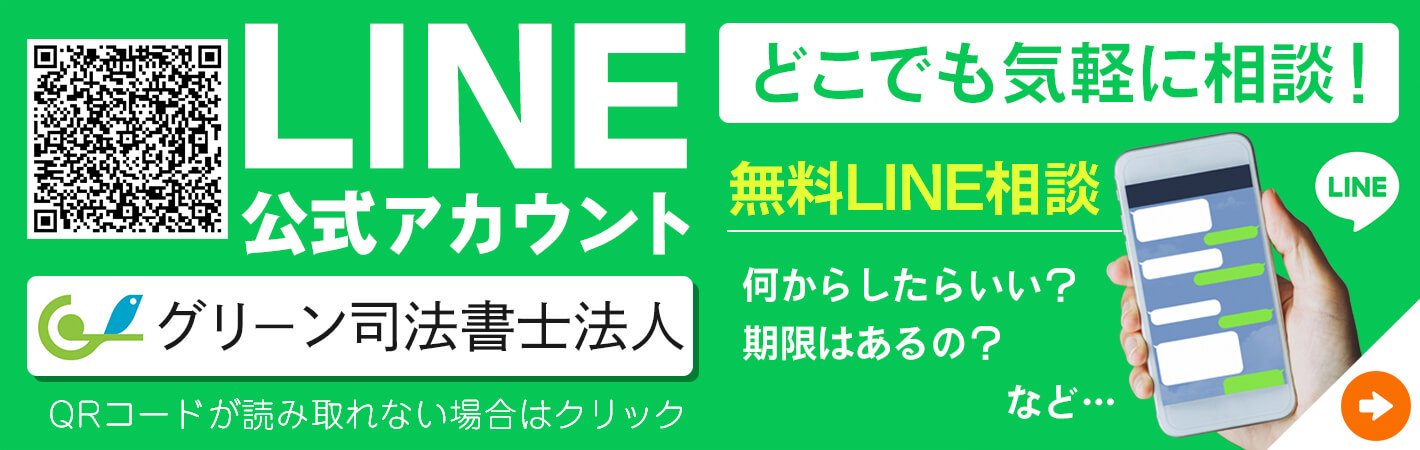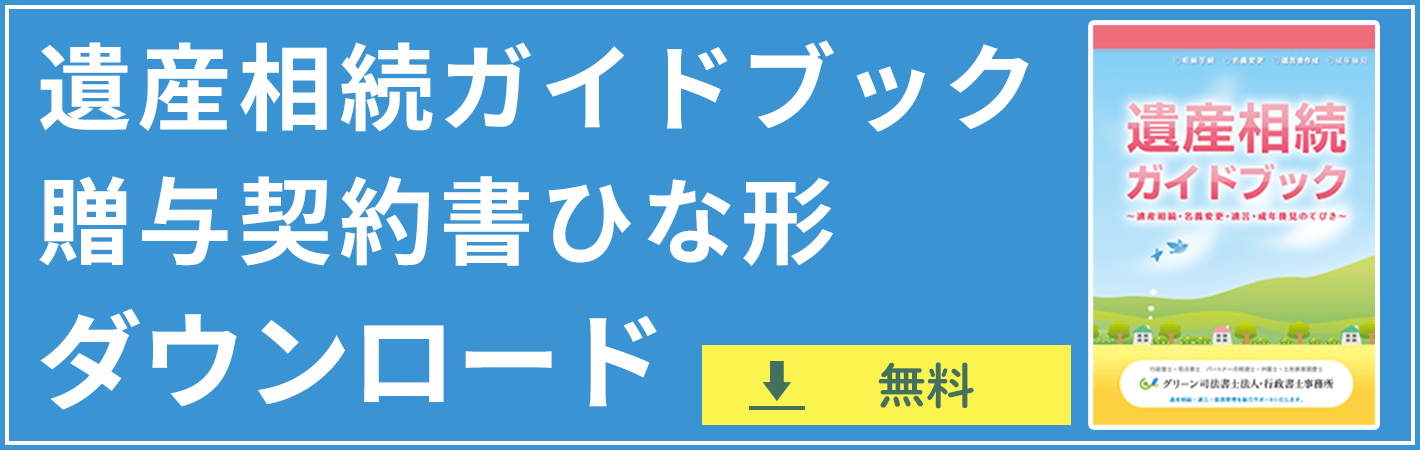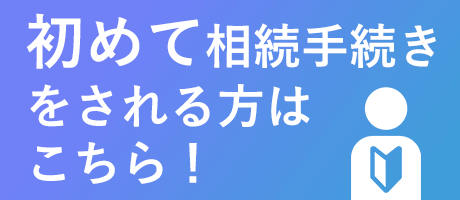不動産の遺産分割を行う|相続財産が不動産だけの場合の対応について

山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
分割できない不動産の遺産分割についてお話ししていきます。
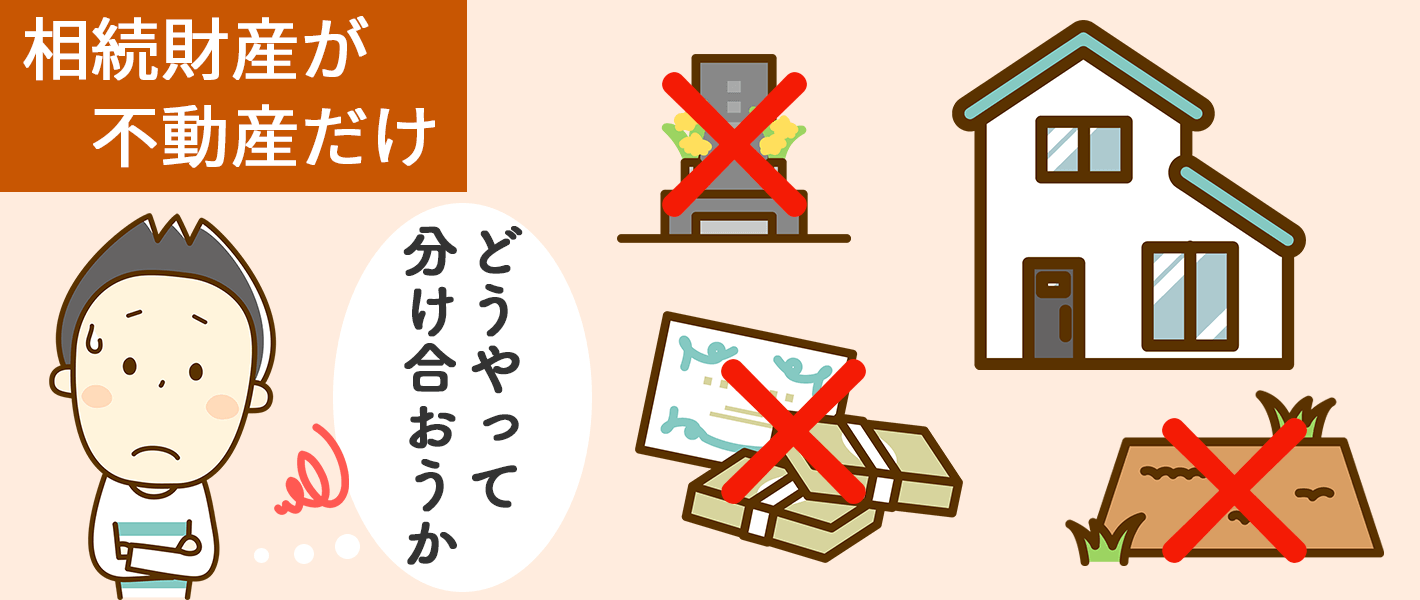
遺言がない場合、相続した不動産は、相続人全員の共有となります。
これを相続人のだれかの単独所有とする遺産分割をしておかないと、今後、不動産を処分する際に支障がでることがあります。
ですので、こちらで紹介する3種類の遺産分割方法の中から選択して不動産の遺産分割を行いましょう。
目次 [ 閉じる ]
不動産の遺産分割方法
- 【現物分割】
そのままの形で引き継ぐ - 【代償分割】
遺産分割・・・代償金を支払って解決する - 【換価分割】
売却したお金を分割する
その他にも共有不動産にする方法もありますが、トラブルの原因になりやすいので、しっかり分割しておくことをおすすめいたします。
不動産の遺産分割方法1/現物分割
1つ目の不動産の遺産分割方法は、現金分割です。
現金分割とは、不動産などの遺産をそのままの形で引き継ぐ方法のことをいいます。
例えば、遺産である土地を2人の相続人で分筆して遺産分割するケースが該当します。
現物分割のメリットは、そのままの形で遺産を受け継ぐことができるので、売却してお金を分割するなどの手間がかからないところです。
デメリットは、分割するのが難しい財産がある場合、公平に分割することが難しく、現物分割には向いていません。
不動産の遺産分割方法2/代償分割
2つ目の不動産の遺産分割方法は、代償分割です。
代償分割とは、不動産など分割できない財産を1人の相続人が取得して、他の相続人には法定相続割合に応じた代償金を支払うことで公平に分割する方法です。
例えば、3人の相続人がおり、3,000万円の価値がある不動産は長男が相続し、残り2人の相続人にそれぞれ法定相続分の3分の1である1,000万円ずつ代償金を払って公平に分割となります。
代償分割は代償金を支払うので公平に分割することができ、トラブルになりにくい遺産分割方法です。
ですが、不動産の評価が必要となり、その評価をもとに代償金の金額が決まるので、評価方法や評価額で不満がでないように気を付けましょう。
また、不動産の相続を希望していても、代償金の支払能力がない場合は、代償分割で遺産分割することができません。
不動産の遺産分割方法3/換価分割
3つ目の不動産の遺産分割方法は、換価分割です。
換価分割とは、不動産を売却して売却金を相続人で公平に分割する方法で、不動産を売却して諸経費を差し引いて手元に残った金額を法定相続割合に応じて分配するのです。
例えば、3人の相続人がおり、2,500万円で不動産が売れて、400万円諸経費がかかった場合、手元には2,100万円残り、法定相続分である3分の1ずつ分割して、1人700万円ずつ受け取ります。
換価分割のように不動産の評価を確認する必要がないので、トラブルに発展する可能性は一番低い遺産分割方法です。
ですが、売却するタイミングを誤ると安く売却してしまうことになってしまいます。また、親が残してくれた不動産を失う寂しさがあります。
不動産や土地の遺産分割のポイント
不動産の遺産分割方法を紹介しましたが、どのような場合に選択するのがおすすめかについてご説明していきます。
相続人の誰かが相続不動産に住んでいる場合は代償分割を選択
遺産に含まれている土地と建物に、故人と一緒に暮らしていた相続人がいた場合、引き続きその家で生活するためには、その相続人が土地も建物も相続するのが一般的です。
ですが、他にも相続人がいる場合は、不動産を相続した相続人の遺産分割の割合が大きくなるので、不公平になってしまう可能性があります。
相続人全員が納得していれば問題ないのですが、そうではない場合は代償分割を選択しましょう。
そして、代償分割を選択した場合、代償として現金を渡す相続人の方は、ご自身の生活に支障がでないかどうかも含めて検討するようにしましょう。
住む予定がなく不動産や土地を手放してもいい場合は、換価分割を選択
亡くなった親と子が別々に生活していた場合、親が住んでいた家に住む予定がないということは少なくありません。
住む予定のない土地や建物を相続しても維持費がかかるので手放したいと考える方もいるでしょう。
そのような場合は、換価分割を選択することをおすすめします。
ですが、場所や条件によっては買い手が見つからない可能性もあり、買い手が見つからない場合は換価できませんので注意しましょう。
また、事前にいくらで売却できるのかも確認しておきましょう。
相続財産が不動産だけ、不動産の遺産分割を行う場合の解決事例一覧
相続のお悩み別一覧
相続に関するよくあるお悩みを紹介しております。
相続に関するよくあるお悩み合わせて読みたい記事
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事