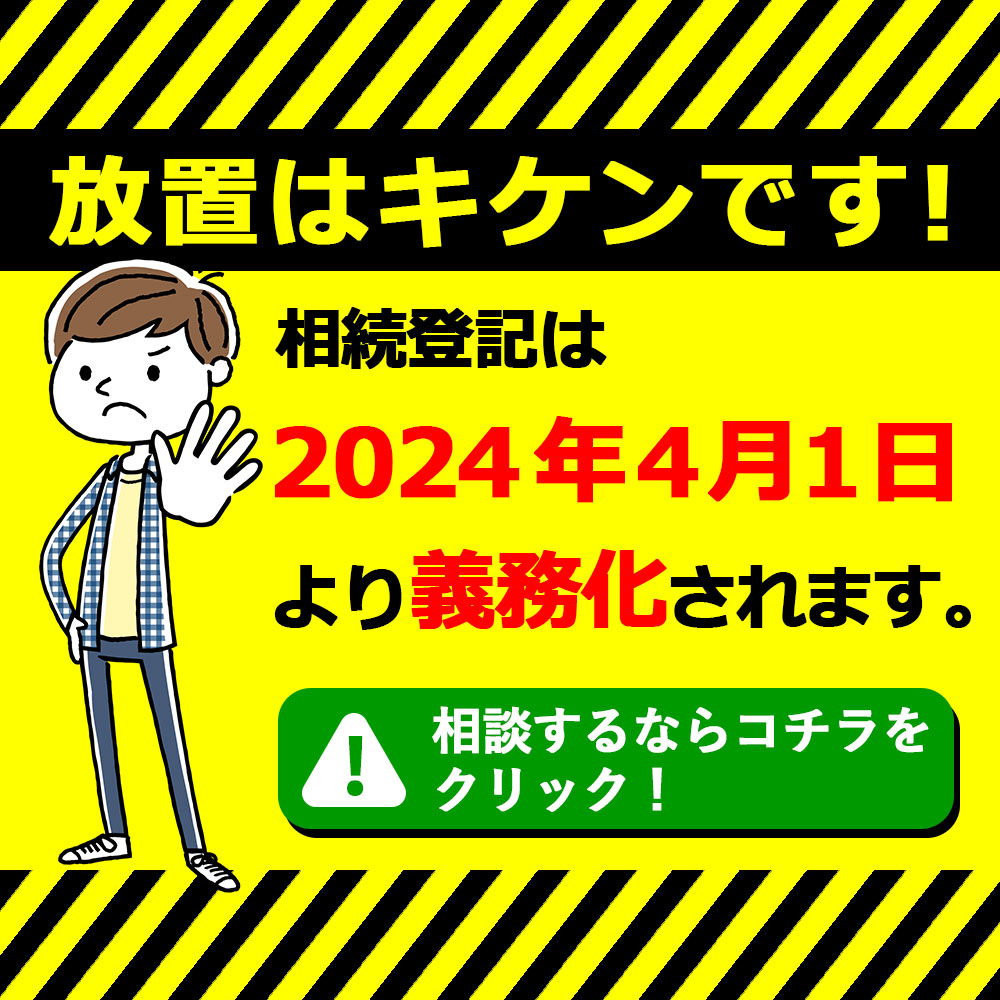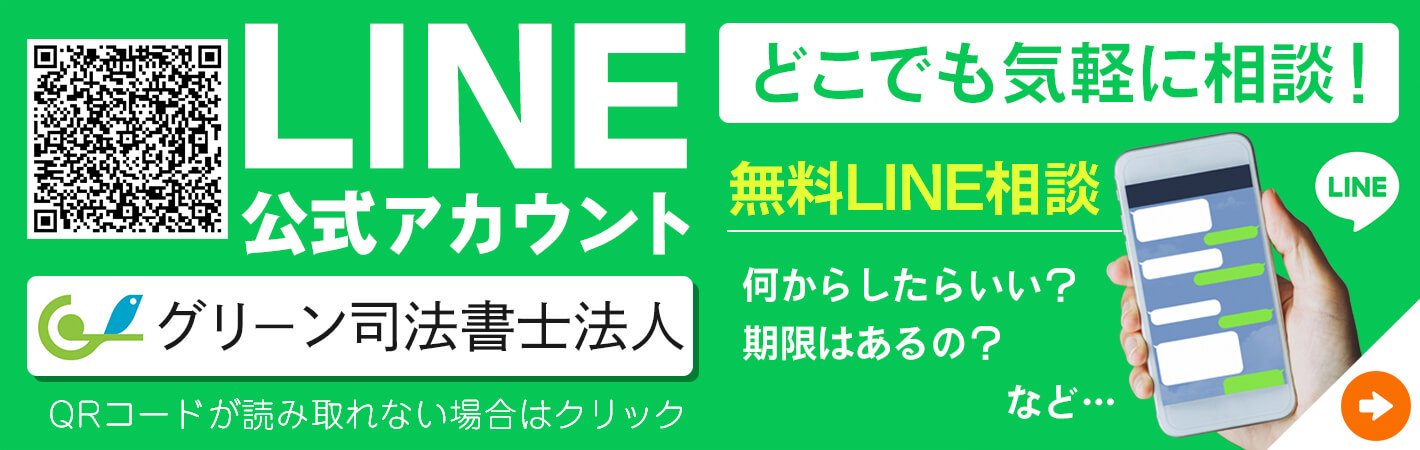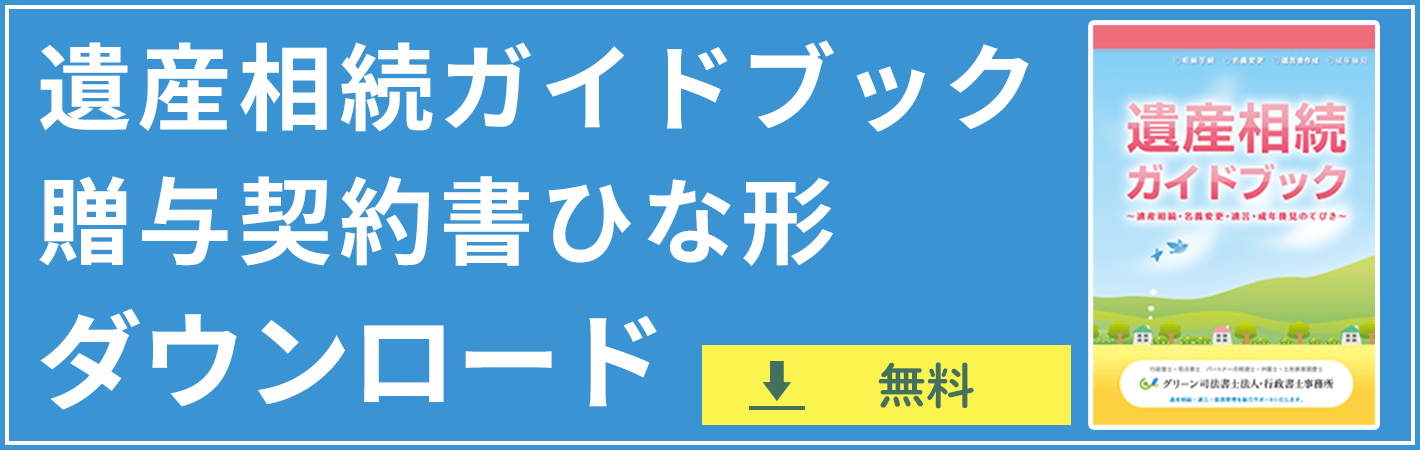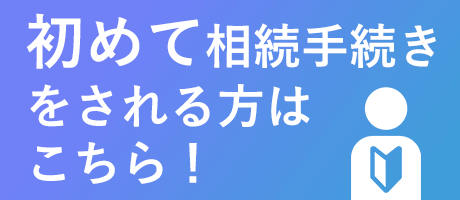【旧】相続登記の上手な進め方と費用について大阪相続相談所の司法書士が解説

山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
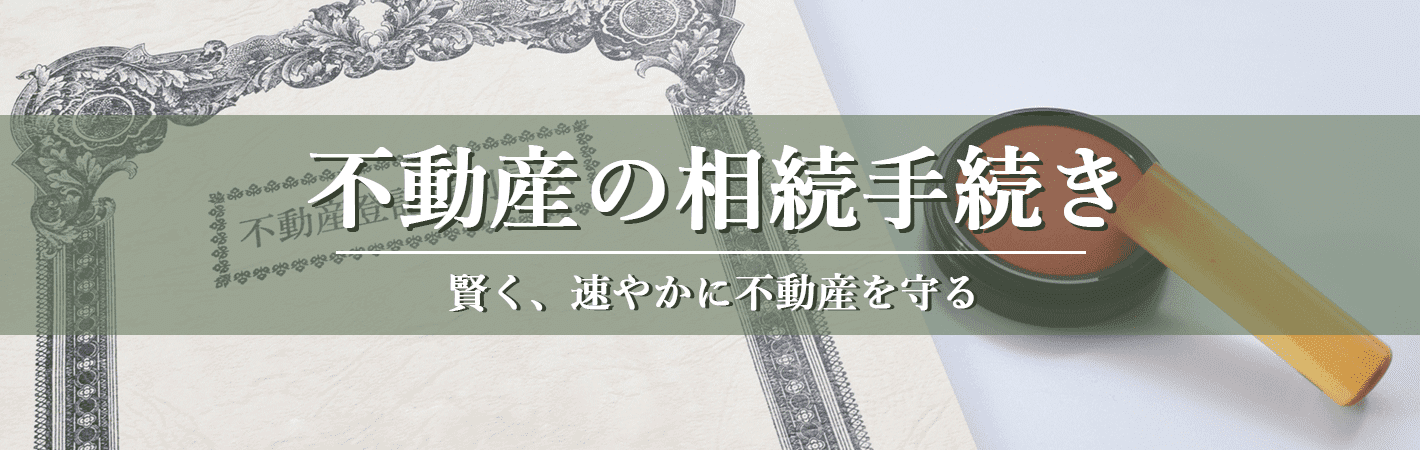
このページでは、相続登記などの不動産相続に関する手続きと、かかる費用を中心に、不動産のプロである司法書士が、わかりやすく解説しています。
上から順に読んでいくだけで、相続登記など不動産相続のすべてがわかります。
不動産をお持ちの方が亡くなって、相続手続きをしないといけないけど、何から手を付けていいかわからない。そんな状況でこのページをご覧になっているのかもしれません。
不動産は、相続財産のなかでも最も重要な財産のひとつです。
相続は、人生の中でもめったに起こらず、なれない手続きではありますが、故人の大事な財産、失敗のないように進めていきたいものです。
相続登記を検討される場合は、専門家に相談されることをおすすめしております。大阪相続相談所では司法書士による無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
目次 [ 閉じる ]
相続登記の手続きに期限はありませんでしたが、2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記手続きを行うように義務化されることが国会で決まりました。
所有者がわからない土地が年々増えており、その問題を解消するための関連法です。
相続登記の義務化に加えて、相続登記の手続きも簡素にすると言われており、管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度が新設されます。
申告しなかった場合は10万円以下の過料に処せられる可能性があるので気を付けましょう。
無料相談!時間制限なし!
- 0120-151-305
<平日>9:00-20:00 <土日祝>9:00-18:00
グリーン司法書士法人運営 - 電話でお問い合わせ
<平日>9:00-20:00 <土日祝>9:00-18:00
グリーン司法書士法人運営 - メールでお問い合わせ


- 相続の専門家にお気軽にご相談ください!

不動産の相続手続きは、大きくは次の様な流れとなります。
- 【ステップ1】
相続関係と相続不動産の調査 - 【ステップ2】
遺産分割・・・不動産を誰が相続するか決める - 【ステップ3】
相続不動産の名義変更登記(相続登記)
では、このステップを1つずつ見ていきましょう
ステップ1/相続関係と相続不動産の調査
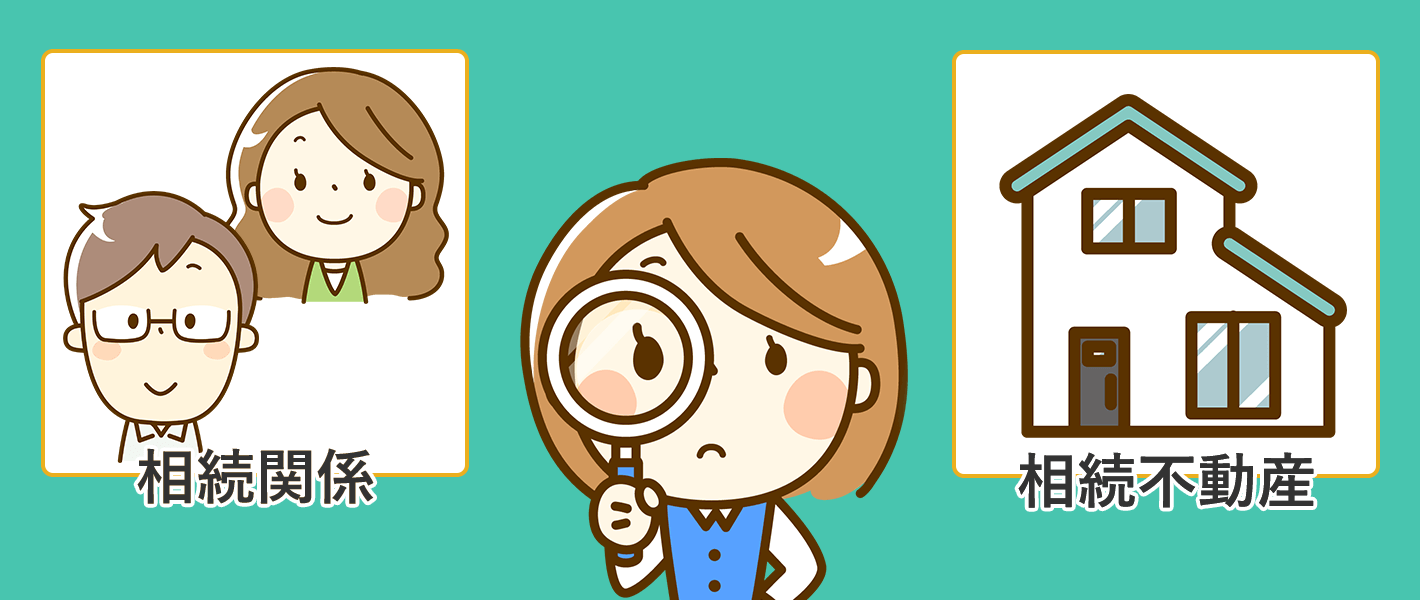
不動産をお持ちの方の相続が発生した場合、最初に各種調査を行うことが必要です。
なぜなら、誰が不動産を相続する「相続人」なのか、そして、家や土地などの権利関係がどうなっているかが分かることで、円滑に不動産相続を進めていくことができるからです。
次の4つの調査に分けてみていきましょう。
- 【調査その1】
相続関係を調べるために戸籍を集める - 【調査その2】
遺言書があるかどうかを確認する - 【調査その3】
相続不動産がどこにあるか調査する - 【調査その4】
法務局で相続不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を取得する
調査その1/相続関係を調べるために戸籍を集める
まずは、自分が相続人かどうか、他に相続人がいるかどうかを確認するために、戸籍を調査します。
というのも、第一に、不動産を相続する権利がなければ、相続登記などの手続きをする必要がないからです。
次に、不動産をどのように遺産分割し、相続登記するかを決めるために、他の相続人が誰なのか把握しておく必要があります。
そもそも、自分が相続人であることを証明できなければ、今後の調査ができないので、まずは、自分が相続人であることを証明できるように、戸籍を集めます。
戸籍は原本還付請求をすれば使い回せることが多いですが、100%ではないので、複数取得しておいた方がいいでしょう。
- ・故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・・・故人の本籍地の市役所で取得(1通450円~750円)
- ・自分の現在の戸籍謄本・・・自分の本籍地の市役所で取得(1通450円)
※本籍地と居住地が同じ場合、次の書類も同時に取得しておきましょう。 - ・故人の最終住所地の戸籍附票・・・故人の本籍地の市役所で取得(1通300円)
- ・自分の住民票・・・自分の居住地の市役所で取得(1通300円)
- ・自分の印鑑証明書(1通300円)
調査その2/遺言書があるかどうかを確認する
次に、あなたが不動産を相続するのかどうか遺言書の有無を確認します。
なぜなら、故人の相続人であっても、故人が不動産について遺言書を作っていたら「遺言書」の内容が優先されるからです。
たとえば、お父様が亡くなられた場合、配偶者(ここでは、お母様)が引き続き家に居住できるように、遺言書で不動産の相続先を配偶者に指定していることが多いです。
その場合、お母様が相続されないと言わない限り、お母様が相続するので、子供が相続登記などを行う必要はなくなります。
遺言書があるかどうかは次のようにして判明します。
優先度と手軽さの順になっていますので、上から順に探してみてください。
- ① 故人の同居家族に聞く
- ② 公証役場で調査してもらう
- ③ 法務局で調査してもらう
- ④ 故人の遺品整理をする
第1に、故人と生活をともにしていた同居家族に遺言書があるかどうかを確認します。
こちらは聞くだけですので、早めに確認しておきましょう。
第2に、遺言書は公正証書で作られていることが多いため、公証役場で遺言書の有無を確認します。
こちらは、全国どこの公証役場でも無料で検索することが可能です。事前に取得する戸籍謄本はここで必要になります。
第3に、法務局にも確認します。
2020年7月10日から、自筆で書いた遺言書を法務局で預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」というものが始まりました。全国どこの法務局でも遺言書が保管されているかを調べることが可能です。
調べる場合は、1回800円の手数料がかかります。
内容まで確認するためには、相続人全員の戸籍や住民票が必要となりますので、遺言書が保管されていることが分かったら、後日書類を集めてから「遺言書情報証明書」を取得しましょう。
こちらは1400円の手数料がかかります。
第4に、故人が自分の家で遺言書を保管していたかもしれないときは、遺品整理をしましょう。
自分でするのが大変な場合は、業者に頼むのもいいでしょう。ほとんどの業者は、文書などをきちんと分けて整理してくれます。
業者選びが心配な場合は、お問い合わせいただければ、大阪相続相談所がご紹介いたします。
相続人調査をして、遺言書の有無を調べ、自分が不動産を相続することが分かったら、次は不動産自体の調査をします。
次のステップでは、故人が所有していた不動産を探す方法を解説します。
調査その3/相続不動産がどこにあるか調査する
相続登記などの不動産相続手続きのためには、「不動産がどこにあるのか、土地の地番、家の家屋番号は何番なのか」を調べる必要があります。
不動産の権利関係を調べるためには、法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を取得しなければいけませんが、これを取得するためには、土地であれば「地番」、建物であれば「家屋番号」という住所とは異なる番号が必要となるからです。
調べる方法は大きく分けて3つあります。
- ①相続不動産の住所から調べる
- ②固定資産税の課税明細から調べる
- ③名寄せ帳から調べる
①相続不動産を住所から調べる
故人の持ち家であれば、住所を法務局に伝えることで、不動産の地番を教えてもらうことが可能です。
これは電話でも教えてもらえるので、持ち家の住所を管轄する法務局に電話をして確認、メモしておきましょう。
②固定資産税の課税明細から調べる
遺品整理の際に、固定資産税の納付書を見つけたら、その表紙が課税明細となっていることがほとんどです。
そこに不動産の地番・家屋番号などが書かれていますので、大事に保管しておきましょう。
③名寄せ帳から調べる
名寄せ帳とは、市役所などが固定資産税の管理のために保有している課税台帳から、故人に関する情報を抜き出した一覧表となります。
たとえば、故人が自分の家も所有しながら、祖父母の家も相続しているかもしれません。
ですが、どこにそれがあるか分からないときは、名寄せ帳を取得することで、市町村単位で調べることが可能です。
また、マンションなどであれば、敷地が明確なことが多いですが、戸建ての場合には、複数の区分の土地にまたがって家が建っていたり、駐車場が飛び地にあったりして、不動産の相続漏れが発生しやすいため、名寄せ帳で調べることが望まれます。
全国の名寄せ帳はとれないので、故人にゆかりのある土地の市町村毎で取得しましょう。
ここでも、事前に取得していた戸籍謄本が必要になります。
調査その4/法務局で相続不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を取得する
相続不動産のありかが分かったら、法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を取得しましょう。
この書面を調べることで、相続する不動産に関する権利関係が判明します。
相続不動産の、家屋番号と地番が分かっていたら、日本全国どの法務局でも全部事項証明書は取得できますし、郵送で取得も可能です。
ですが、間違うと郵送で何度もやりとりすることになるので、最寄りの法務局に行くのがいいでしょう。費用は印紙で600円かかります。
クレジットカードを保有されている方は、全部事項証明書に書かれていることをオンラインで閲覧することも可能です。
証明書としては使えませんが、調査段階では十分ですので、是非利用してください。こちらは費用も334円と安いです。
登記情報提供サービス一時利用はこちら全部事項証明書を見ることで、相続不動産に関する権利関係のほとんどが判明します。
「誰が所有者なのか」から、たとえば、次のようなことまで判明します。
- ・住宅ローンの契約が残っており、抵当権がついているか
- ・住宅の敷地が借地だったか
- ・故人の兄弟と共有の不動産だったか
ステップ2/遺産分割・・・誰が不動産を相続するか決める
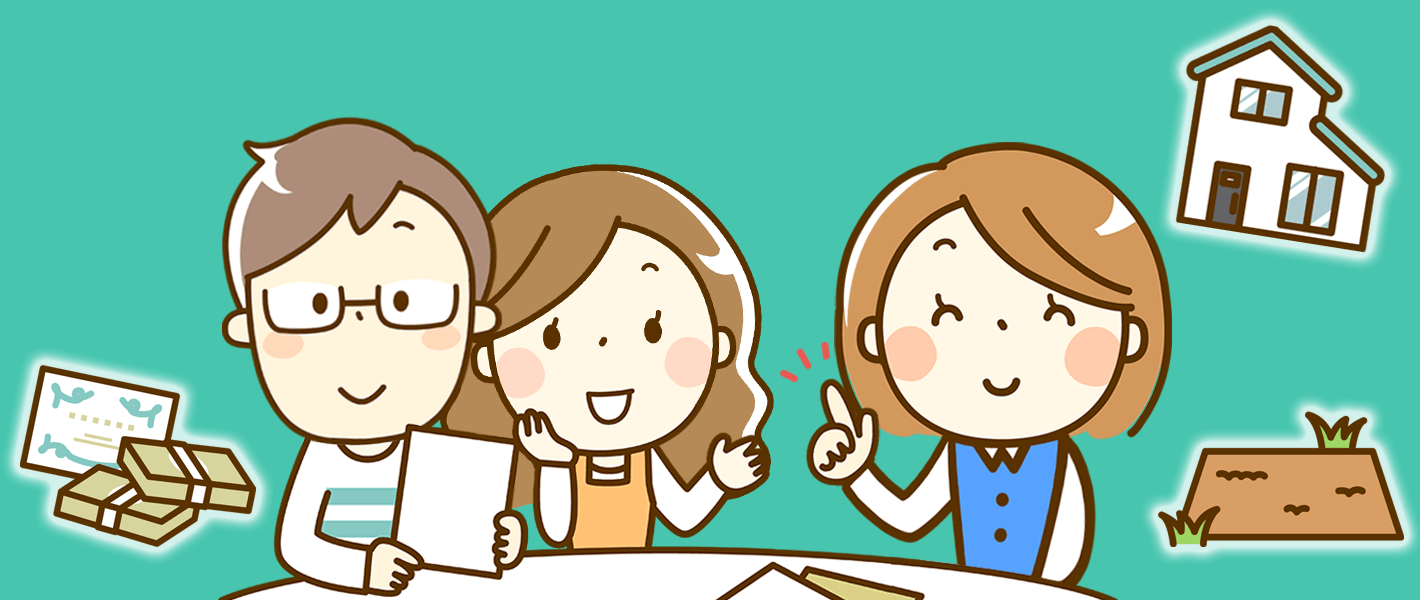
不動産の相続について、事前調査が完了したら、次のステップでは「誰が不動産を相続するか」を決めるために「遺産分割協議」をします。
遺言書がなく、相続人が複数人いる場合、誰が不動産を相続するかを「遺産分割協議」という話し合いで決めることになります。
法律の割合で、そのまま共有にする方法もありますが、共有は後日争いの種になりやすいので、遺産分割協議でしっかり分けておくことをおすすめします。
遺産分割の要件
遺産分割協議をするためには、いくつか守らなければならないルールがあります。ルールを守らないと、遺産分割が「無効」となるので、十分注意してください。
- ① 相続人の全員が参加が必要
- ② 参加者には正常な判断が必要
- ③ 利益相反禁止
①相続人全員の参加が必要
遺産分割協議をするためには、「相続人全員」が参加する必要があります。
音信不通の相続人がいるからと、その人を省いて行った遺産分割協議は「無効」となります。
もし、遺産分割をしないうちに相続人が死亡した場合、相続人の相続人も参加する必要があり、権利関係が複雑になるため、相続トラブルに発展する可能性があります。
トラブル回避のため、遺産分割協議は早めに行うのがいいでしょう。
家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
不在者財産管理人とは、行方の知れない人の財産を、本人に代わって管理する管理人のことをいいます。
ただし、単に電話に出てくれないなどの場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判を求めて裁判をする必要があります。
②遺産分割協議への参加者には正常な判断力が必要
認知症で正常な判断ができない人が相続人に含まれている場合、その人は遺産分割協議には参加することができません。
家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらいます。
成年後見人とは、認知症などで正常な判断ができなくなった人の法律行為を全面的に代理する人のことをいいます。
成年後見人に代わりに遺産分割協議に参加してもらうことになります。
③利益相反禁止
たとえば、親と未成年の子供がともに相続人になっているとき、親が子供を代理して遺産分割協議をすることは禁止されています。
同じく、成年後見人と被後見人である認知症の方がともに相続人になっているとき、成年後見人が被後見人を代理して遺産分割協議をすることも禁止されています。
家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらいます。
特別代理人とは、自分と自分が代理する人との契約など、公正な代理行為が期待できないときに、本来の代理人が行うべきことを代わって行う特別な代理人のことをいいます。
または、自分は財産がいらないという場合には、自分は相続放棄するという方法があります。こちらも家庭裁判所に対して手続きをすることになります。
遺産分割の方法
遺産分割の要件が満たされたら、相続不動産をどのように分けるのか実際に遺産分割の協議を行います。
遺産分割の方法は、大まかに次の3つに分類されます。
- ① 現物分割
- ② 代償分割
- ③ 換価分割
①現物分割
現物分割は文字通り、現実の物を分ける遺産分割方法です。
たとえば、不動産が2つあるときに、長男はA不動産を、次男はB不動産を相続する、といった分け方です。
わかりやすい反面、相続する財産に価格差があったりすると、不公平が生じて話がまとまらない可能性があります。
②代償分割
代償分割は現物分割を補充するような分割方法です。
さきほどのケースでいうと、A不動産が2,000万円、B不動産が1,000万円のときに、長男が2,000万円分相続するかわりに、次男に500万を代償金として支払うことを遺産分割の合意の内容に含める、といった遺産分割方法となります。
③換価分割
換価分割とは、文字通り、相続不動産を換価(売却)して、売却代金を分けるという遺産分割方法です。
売却代金は金銭ですので、分けることが非常に簡単になります。
すでに自分の家を持っていて、不動産はいらないという場合に効果を発揮する遺産分割方法です。
遺産分割のコツ
遺産分割で相続不動産の分け方を決めるとき、共有にする選択もできます。
ですが、共有にしてしまうと今後不動産を処分したり、有効活用したりしようとしたときに、共有者の意見が食い違って困るということが起こりうるので、不動産については、それぞれが単独で所有するように分けることをおすすめします。
すぐに遺産分割協議書をつくる
遺産分割協議で誰が不動産を相続するかが決まったら、それを「遺産分割協議書」という文書にして、相続人全員の「実印」で署名捺印をしておきましょう。
後日の争いを防ぐための証拠を残す必要がありますし、法務局に相続登記の申請をする際に、「実印の遺産分割協議書は必須の文書」だからです。
また、いったん合意しても人間ですから翻意することがあるため「すぐに」作ることを心掛けてください。
たとえば、遺産分割協議の後に、遺産分割協議書を作らずにいたら、相続した土地の一部が大きく値上がりしたときを考えてみてください。
ほかの土地を相続した人が「不公平だ」と、ハンコを押してくれなくなるということが想像できるでしょう。
遺産分割協議書の記載事項
遺産分割協議書をつくる際に、書いておかなければならない最低限の記載事項をお教えします。
①タイトル
この文書は何なのかを明確にするため「遺産分割協議書」とタイトルを書きましょう。
②故人についての情報
この文書は「誰の相続」についての遺産分割協議書なのかを明確にするため、故人の情報を書いておきます。
こちらも最低限、故人の「氏名」、「生年月日」、「本籍地」、「死亡日」などを記載しておきます。
③相続する財産を特定する内容
後日の争いを防ぐために、相続する財産を特定する情報を必ずいれておきます。
不動産の相続であれば、調査で取得した「登記事項証明書」をもとに、次のように記載します。
| 【土地】 | 所在:○○市○○町○丁目 地番:○番○号 地目:○○ |
|---|---|
| 【建物】 |
所在:○○市○○町○丁目 家屋番号:○番○ 種類:○○ 構造:○○造○○階建 床面積:1階 ○㎡ 2階 ○㎡ 3階○㎡ |
| 【マンション】 |
一棟の建物の表示 所在:○○市○○町○丁目 建物の名称:○○マンション 専有部分の建物の表示 家屋番号 ○○町○丁目 建物の名称:○○○ 種類:○○ 構造:○○造○○階建 床面積:○階部分 ○㎡ 敷地権の目的である土地の表示 土地の符号 ○ 所在及び地番:○○市○○町○丁目○番○ 地目:宅地 地積:○㎡ 敷地権の表示 土地の符号:○ 敷地権の種類:○○権 敷地権の割合:○分の○ |
④遺産分割の内容
③で特定した財産を誰がどのように相続するかを記載します。
⑤各相続人の署名・捺印・日付
相続人全員が遺産分割協議書に署名と捺印(実印)を行う必要があるので、各人の署名欄・捺印欄を書いておきましょう。
また、遺産分割協議の成立日を明らかにするために、日付も書いておきましょう。
※あくまでも、不動産相続の名義変更登記に耐えうる最低限の記載事項となります。
ステップ3/相続不動産の名義変更登記(相続登記)
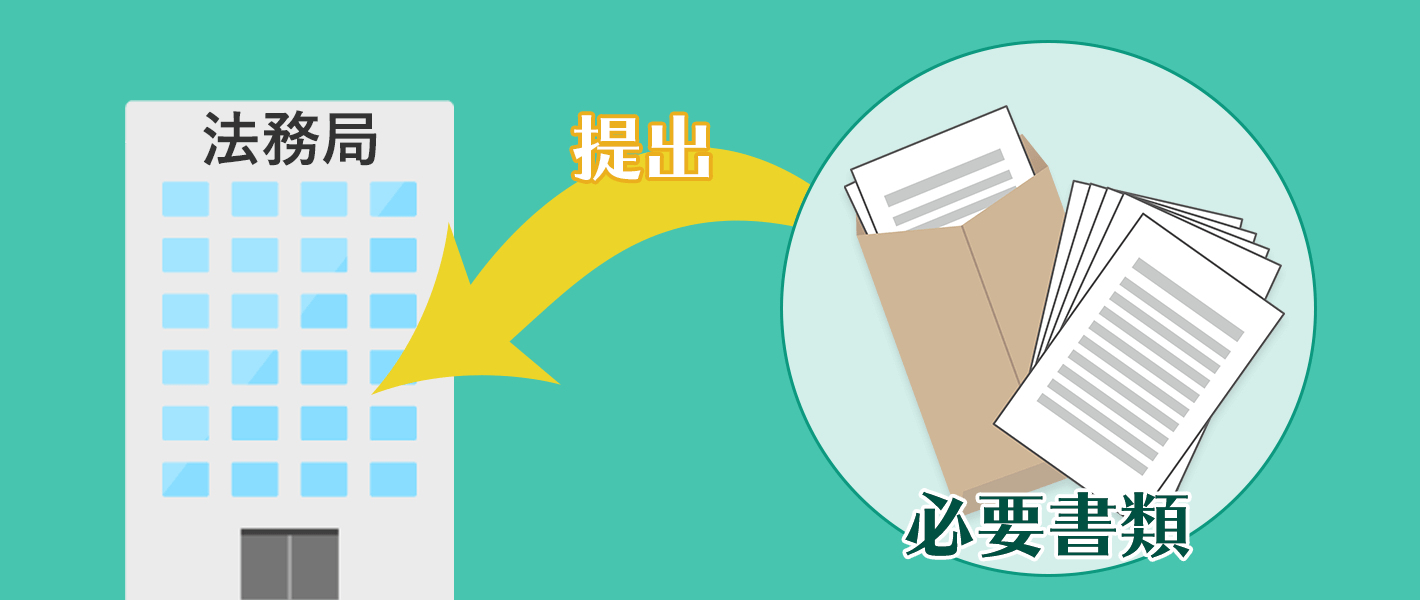
遺産分割協議書まで作成できたら、さっそく法務局に名義変更登記申請を行います。
必要書類は次のとおりです。
名義変更登記に必要な書類
- ・登記申請書
- ・遺言書
- ・故人の死亡記載がある戸籍謄本
- ・相続する人の戸籍謄本(故人との相続関係がわかるもの)
- ・故人の最後の住所証明 住民票か戸籍附票
- ・相続する人の住民票
- ・登記申請書
- ・遺産分割協議書
- ・相続関係説明図
- ・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・相続人の戸籍謄本
- ・故人の最後の住所証明 住民票か戸籍附票
- ・相続する人の住民票
- ・登記申請書
- ・相続関係説明図
- ・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・相続する人の戸籍謄本
- ・故人の最後の住所証明 住民票か戸籍附票
- ・相続する人の住民票
※申請書については、法務局がそれぞれのパターン別にひな形を公開しています。
※司法書士に頼んだり、親戚の登記を代わりに行ったりする場合は、別途「委任状」が必要となります。
登録免許税を用意する
相続不動産の名義変更登記を申請する際には、評価証明書に書かれている価格の0.4%を登録免許税として法務局に納める必要があります。
原則として、申請書に収入印紙を貼ることで納税します。
相続不動産の価格が5000万円の場合には、登録免許税として20万円が必要となります。
登録免許税については下記ページで説明しておりますので、ご参考にしてください。
登記申請をする
必要書類の収集、作成が終わったら、申請書と必要書類をひとまとめにして法務局に提出します。これを「登記申請」といいます。
登記申請の提出先は「相続不動産の所在地を管轄する」法務局となります。
申請のやり方は、「窓口申請」、「郵送申請」、「オンライン申請」の3種類があります。
窓口申請は、申請書を管轄法務局の窓口に持参する登記申請方法です。物件が近くにある場合には、窓口に持参された方が確実です。
郵送申請は、申請書を管轄法務局に宛てて、郵送する登記申請方法です。
物件が遠方にある場合には、書留またはレターパック510を用いて郵送で申請をすることも可能です。
権利証などを返信してもらわなければならないので、返信用封筒(こちらも書留またはレターパック510)をつけておきましょう。
オンライン申請は、パソコンなどで作った申請データに電子署名して、インターネットで申請する登記申請方法です。
個人の電子証明書を取得している方のみ利用が可能です。
電子証明書を取得している個人はほとんどいらっしゃらないのと、結局申請書以外の書面は郵送しなければならないので、積極的には勧めておりません。
相続不動産の相続登記が完了すると「登記識別情報」と呼ばれるコードが書かれた書面がもらえます。
この書面は「権利証」に変わるもので、同様に重要な書類なので、絶対になくさないようにしましょう。
相続登記(不動産の名義変更)が義務化されます
今まで相続登記の手続きに期限はありませんでしたが、2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記手続きを行うよう義務化されることとなりました。
所有者不明土地が年々増えており、国の調査によれば国土の約2割に上ると発表されており、所有者と連絡がとれないため、公共事業や都市部の再開発の妨げとなると問題になっています。
その所有者不明土地の問題を解消するための関連法が国会で可決されたことにより、相続登記が義務化されることになり、相続登記の手続きも簡素化されるようです。
管理が難しい場合は、相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設したり、名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設けたりと、所有者不明の土地の取引の機会を増やすことで休眠状態にある不動産の流動性を高める狙いがあります。
これまで、相続登記手続きでは相続人全員の戸籍などを集める必要があったが、不動産登記法が改正され、相続人が複数人いても、そのうちの1人が申し出れば簡易に手続きできる制度が設けられます。
そして、手続きが簡易になる代わりに土地の相続時の名義人変更を義務として、相続した人を国が把握できるようにするようです。申告しなかった場合は10万円以下の過料に処せられる可能性があるので気を付けましょう。
相続登記がまだだけど、手続きや改正内容などはよくわからないとお困りの場合は、大阪相続相談所は無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/9:00-18:00]グリーン司法書士法人運営
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事